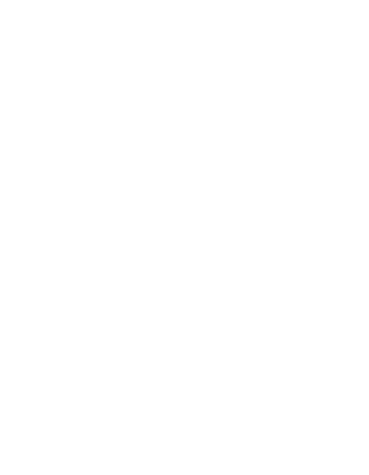いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。
今年は3月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。
今回は【ボケ】についてお話致します。
ボケは、庭木や盆栽、生け垣、切り花として観賞され、200を超える品種が栽培されています。
また、観賞だけではなく、香りのよい果実を使って果実酒やジャムをつくることができます。
ボケ属は、日本原産のクサボケ(Chaenomeles japonica)、中国のマボケ(C. cathayensis)とボケの3種からなる落葉低木類です。
ボケの渡来時期は、平安初期以前であるとされます。元禄年間(1688~1704年)の園芸書には、淀ボケや八重ボケなどの多少の品種が記録されている程度で、明治時代にもほとんど園芸品種は発達しませんでした。
その後、大正時代に、新潟県新潟市と埼玉県川口市を中心としたボケのブームが起こり、‘東洋錦’や‘日月星(じつげつせい)’が作出されました。
さらに昭和40年ごろから、数多くの品種が発表されるようになり、ボケの第二次ブームが起こりました。
【栽培環境・日当たり・置き場】
日当たりのよい場所で、乾燥しすぎない土壌であれば、土質を選ばずによく生育します。
とげがあるので、人や動物の侵入止めの生け垣にすることができますが、庭に植える場合は、ケガをしない場所を選ぶ必要があります。
鉢植えは、通年よく日の当たる戸外で管理し、開花期には室内に取り込んで観賞します。
ただし、夏の高温期には、土壌の乾燥を避けるために、半日陰に移動させます。
【水やり】
植えつけからまもなくは、乾いたら水を与えますが、真夏の特に乾燥するとき以外、水やりは不要です。
鉢植えは極端に乾燥させると、葉が枯れたり、蕾が落ちたりします。
浅鉢に植えて販売されていることが多いので、水は落葉期には少なめ、春と秋は1日1回程度、夏は十分に与えて、乾燥させないように管理します。
【肥料】
庭植えは1月上旬から2月下旬に寒肥として、緩効性の化成肥料や固形の発酵油かすを施します。
鉢植えは、開花後のお礼肥として4月上旬から5月上旬に、また、株が充実する9月下旬に、緩効性の化成肥料や固形の発酵油かすを施します。
【病気と害虫】
病気:赤星病、根頭がん腫病
最も注意が必要なのが赤星病で、新葉にオレンジ色の斑点が入ります。
ビャクシン類などから伝染するので、これらの近くに植えるのは避け、発生した場合は、殺菌剤を散布します。
根頭がん腫病は、春に植え替えをすると発生しやすくなるので注意します。
害虫:アブラムシ類、カイガラムシ類
春から秋までアブラムシ類やカイガラムシ類が発生することがあるので、剪定して風通しをよくし、予防します。
【用土(鉢植え)】
水もちと水はけのよい用土を使います。
赤玉土小粒5、鹿沼土または軽石の小粒3、腐葉土またはピートモス2で混合した用土などを使います。
【植えつけ、 植え替え】
植えつけ、植え替えともに、9月下旬から11月下旬に行います。
庭への植えつけは、根鉢の大きさの倍の深さと幅の植え穴を掘り、腐葉土や完熟堆肥などを混ぜ入れて行います。
根鉢のまわりに十分に水を注ぎ、棒などでつついて根と植え土をなじませます。ぐらつく場合は支柱を立てます。
鉢植えは2~3年に1回、植え替えます。
根をていねいにほぐして、1/3程度をハサミで切り詰め、一回り大きな鉢に植え替えます。
【ふやし方】
タネまき:ボケの野生種は、タネでふやすことができます。
秋に熟した果実を収穫し、水で洗って果肉を落として、赤玉土小粒などにすぐにまきます。
戸外に置き、乾かさないように管理すれば、春に発芽します。
さし木:9月上旬から10月下旬に、その年に伸びた枝を使ってさします。10cmほどの長さで枝を切り、2時間ほど十分に水あげをして、赤玉土小粒や鹿沼土小粒、あるいはさし木用土にさし、風が当たらない日陰に置き、水を切らさないように管理します。
【主な作業】
剪定:剪定の適期は4月下旬から5月下旬、あるいは12月です。
枝がよく伸びるため、鉢植えの株は剪定によって樹形を整えます。開花後に花がらを切り取り、そのときに伸びている枝も1cm程度の長さで切り詰めて、新しい芽を出させます。
12月に蕾が下部についている枝は、蕾を残して10cm程度の長さになるように剪定し、蕾のついてない枝は、1cmの長さで切り詰めます。
庭植えの株は、花後に剪定して樹形を整え、落葉期に枯れ枝や徒長枝を切り除きます。
———————————
庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。
自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!
約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!
是非お問い合わせください!
———————————