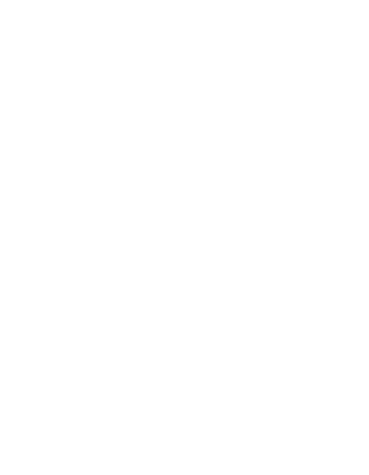いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。
4月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。
今回は【ペチュニア】についてお話致します。
ペチュニアはコンテナや花壇などでおなじみの草花です。
枝垂れるものやこんもりと茂るもの、大輪~小輪、八重咲きなど、いろいろな園芸品種があり、毎年育てていてもあきません。
成長が早くて丈夫なので、初心者にもおすすめです。
南アメリカに自生するペチュニア・アキシラリス、ペチュニア・インテグリフォリアをもとに、ヨーロッパやアメリカで品種改良が進み、多様な品種がつくり出されました。
太平洋戦争前には世界に先駆けて日本の種苗会社が八重咲き品種の商業化に成功し、注目を集めました。
1985年ごろからは品種改良に、ほふく性のペチュニア・アルチプラーナなどを利用することで、それまで実生系(タネから育てる系統)のみだったペチュニアに、栄養系(さし芽でふやせる系統)の園芸品種が誕生しました。
従来の実生系とは異なり、雨に強く大きく育つため大人気となり、ヨーロッパの窓辺を変えたと称されたこともあります。
さし芽をして冬越しさせれば多年草として扱えますが、次第にウイルス病に侵されて観賞価値が下がるので、新しい苗を購入してください。
葉に細かい毛があり、べたつきますが、このべたつきは病害虫から身を守ることに役立っています。
【栽培環境・日当たり・置き場】
鉢植えは、通年、日当たりと風通しのよい場所で管理します。
病気の原因となる泥はねを防ぐために、鉢を土の上に直接置くのを避けたり、少し高い場所に置いたりするとよいでしょう。
冬越し用の小苗をさし芽でつくる場合や、秋にタネをまく場合、12月から4月ごろまでは、日当たりのよい室内で管理します。
寒風の当たらない南向きの日だまりを選んで霜よけを行えば、戸外で冬越しさせることもできます。
庭植えは、日当たりのよい場所を選びます。マルチングをしたり、レイズドベッドのような一段高くなった花壇に植えつけたりすると、泥はねを防ぐことができます。
【水やり】
鉢植えは、土の表面が乾いたらたっぷり与えます。
【肥料】
鉢植え、庭植えともに元肥として緩効性肥料を忘れずに施します。
多肥を好むので、3月から11月の生育期は緩効性肥料を定期的に追肥し、液体肥料も2週間に1回程度施してください。
【病気と害虫】
★病気:灰色かび病
雨が続くと発生します。
花がらや枯れ葉をこまめに取り除いて予防します。
★害虫:アブラムシ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ
アブラムシは、1年を通じて発生します。
ウイルス病を媒介するので、よく観察し、発生したら防除しましょう。
オオタバコガやハスモンヨトウは、夏から秋にかけて幼虫が蕾や花を食害します。
【用土(鉢植え)】
赤玉土小粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土など、水はけがよく有機物に富んだ土で植えつけます。
弱酸性の土を好むので、石灰などは施しません。
市販の培養土でも育てることができますが、生育がよくない場合は赤玉土を2~3割加えたり、酸度無調整のピートモスを2~3割加えたりして、酸度を弱酸性にします。
【植えつけ、 植え替え】
黄ばんだ葉や花がらを取り除いてから植えつけます。
深植えにしないよう注意しましょう。
梅雨明けから9月にかけて植えつけると、秋に立派な花が咲きます。
【ふやし方】
★タネまき:適期は3月から5月と、9月です。
9月にまく場合は、室内や温室などで冬越しさせ、春に植えつけます。
★さし芽:適期は3月から7月と、9月から10月です。
冬越し用の小苗をつくる場合は、9月から10月にさします。
【主な作業】
★花がら摘み:3月から11月に行います。
こまめに取り除くのが理想ですが、面倒なときは切り戻しを兼ねて、花がらが目立つ枝ごと切り取るとよいでしょう。
★葉の整理:大きく育った葉が株元を覆うと病気が発生しやすくなるので、取り除いて風通しをよくします。
★摘心:植えつけ2週間後に行います。先端の芽を切ることで、側枝が伸びて花数が多くなります。
★切り戻し:適期は梅雨前で茎の長さ1/2を目安に切ります。
———————————
庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。
自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!
約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!
是非お問い合わせください!
———————————