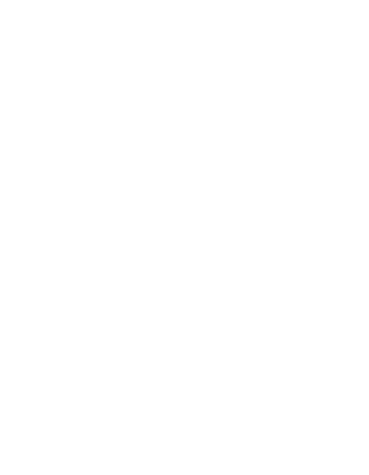いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。
今年は3月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。
今回は【カランコエ】についてお話致します。
カランコエは、花形や色のバリエーションに富み、とても丈夫な植物です。古くから鉢花として楽しまれてきました。
カランコエの多くはマダガスカル原産で暑さに強いので、夏の花壇でも重宝します。開花調整をしたものが通年出回っていますが、本来は日が短い時期に花が咲く短日性植物。
寂しくなりがちな冬の時期に花を咲かせ、室内でも元気に育ってくれます。開花時期も長く、冬中たっぷり楽しめるのもうれしいところです。
新たな品種も続々と誕生しており、華やかな八重咲きや定番の一重咲き、ベル形などさまざまなものがあります。
園芸初心者でも気軽に育てやすく、他の植物の寄せ植えにもおすすめです。
カランコエ属の植物はアフリカ南部、東部、アラビア半島、東アジア、東南アジアに約100種が分布しています。
マダガスカル原産のカランコエ・ブロスフェルディアナをもとに改良された園芸品種が最も一般的で、人工的に開花調節されたカラフルな鉢植えが一年中、店頭に並んでいます。
同じくマダガスカル原産のカランコエ・ミニアタとカランコエ・グラシリペスをもとに改良された、ベル形の花をつける園芸品種も冬に出回ります。
寒くなると紅葉する姿が美しい朱蓮(カランコエ・ロンギフローラ・ユッキネア)、全体が白い毛で覆われた月兎耳(カランコエ・トメントーサ)、葉から芽が出ることで人気のある「ハカラメ」(セイロンベンケイ)などもカランコエ属の仲間です。これらは多肉植物として親しまれています。
【栽培環境・日当たり・置き場】
一般に鉢植えで育て、通年、日なたで管理します。
6月から10月は雨の当たらない戸外で、11月から5月は室内の日当たりのよい場所で管理してください。
日が短くなると花芽をつける性質があるので、秋以降は、夜間照明がある場所に置くと花が咲かないことがあります。
また、ベル形の花を咲かせるものは、霜の当たらない戸外で11月下旬まで管理すると、花芽がつきやすくなります。
【水やり】
6月から8月と、12月から4月は乾かし気味に管理します。
5月と、9月から11月は、用土の表面が乾いたら、たっぷりと与えます。
乾燥には非常に強いものの、過湿に弱いので、乾かし気味に管理します。
【肥料】
5月から9月に緩効性化成肥料を、10月から12月に液体肥料を施します。
【病気と害虫】
病気:うどんこ病、灰色かび病
うどんこ病は、春と秋に、風通しが悪いと発生します。
灰色かび病は、11月から5月に、低温多湿時に発生します。
無加温フレームで冬越しさせると、低温多湿になりやすいので特に注意が必要です。
害虫:カイガラムシ、アブラムシ
カイガラムシは、3月から11月に、風通しが悪いと発生します。
発生の初期にこすり落とすとよいでしょう。
アブラムシは、通年、新芽と蕾に多く発生します。
【用土(鉢植え)】
市販の多肉植物用培養土のほか、赤玉土小粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土など水はけのよい用土に、リン酸分の多い緩効性化成肥料(N-P-K=6-40-6など)を5g/リットル混ぜるとよいでしょう。
【植えつけ、 植え替え】
5月から6月と、9月が適期です。
2年に1回ぐらい、切り戻しと同時に植え替えます。
根鉢をくずし、古い土と根を半分程度落として、深めに植えつけます。
市販の株はピートモス主体の用土で植えられていることが多く、家庭では過湿、過乾燥になりやすく管理が難しいので、入手した株の花が終わりしだい、赤玉土や軽石を主体とした水はけのよい用土に植え替えるとよいでしょう。
【ふやし方】
さし芽:4月から7月、9月が適期です。用土は酸度調整済みピートモスや、さし芽用の土など、肥料分が少なく清潔なものを用います。
一部の種類は葉に子株ができるので、子株を切り離して植えつければ簡単にふやすこともできます。
【主な作業】
花がら摘み:1月から5月に行います。
切り戻し:5月から6月と、9月に行います。春の切り戻しは、花後の花茎の切り取りを兼ねます。
———————————
庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。
自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!
約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!
是非お問い合わせください!
———————————