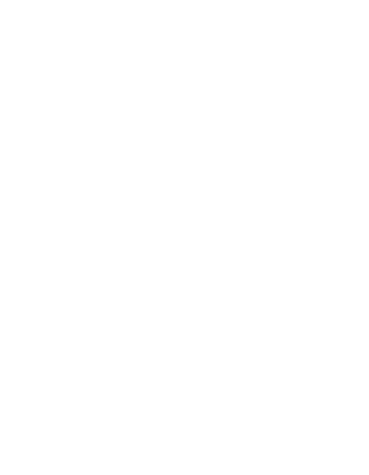いつも弊社のホームページを閲覧頂き、誠にありがとうございます。
今年は2月が旬の野菜・果物・花をご紹介致します。
今回は【プリムラ】についてお話致します。
サクラソウ属の植物は500~600種があるとされており、観賞価値の高いものが多いグループです。
プリムラ・マラコイデスは中国の雲南省原産の一年草です。
株全体に白い粉がつくことから、ケショウザクラ(化粧桜)という和名がつけられています。暑さに弱いので、6月から7月もしくは9月にタネをまいて、翌年の早春からの花を楽しみます。小輪品種(花の小さい系統)と、大輪品種(花が大きく葉がごわごわした系統。
花色が豊富)に大別することができます。
小輪品種はこぼれダネでも毎年よく咲きますが、大輪品種はタネが少量しかできず、耐寒性も弱いので、人工的にタネをまいて、防寒して冬越しさせる必要があります。
【栽培環境・日当たり・置き場】
鉢植えの場合は、夏にタネをまいてできた苗を、秋の彼岸ごろまでは半日陰で管理し、それ以後は日なたで管理します。
大輪品種は寒さに弱いので、冬は凍らせないように防寒します。
小輪品種は凍ると葉が白く枯れますが、寒風に当てなければ戸外で冬越しできます。
凍ると花が傷むので、霜の当たらない軒下で管理しましょう。厳寒期に入手した開花鉢は、室内の日当たりのよい場所で管理しますが、室温が高いと花が早く終わってしまうので、日中は風通しのよい、加温していない室内に置きましょう。
夏は雨の当たらない涼しい半日陰で管理し、秋以降は再び日なたに戻します。
庭植えの場合、小輪品種は戸外で冬越しできるので、秋に南向きの日だまりのような場所に植えつけます。
大輪品種は庭植えには向きません。
【水やり】
鉢植えの場合は用土の表面が乾いたら、たっぷりと与えます。
庭植えの場合は、特に水やりの必要はありません。
【肥料】
10月から4月は、緩効性化成肥料(N-P-K=12-12-12など)を施してください。
次々に花を咲かせるにはたくさんの養分が必要です。
1月から4月の開花期は液体肥料(N-P-K=6-10-5など)も施し、肥料切れさせないようにしましょう。
夏越し中の6月から7月と9月は、規定の濃度よりも薄めの液体肥料を施します。
【病気と害虫】
★病気:灰色かび病
灰色かび病は低温多湿になると発生するので、晩秋から春まで注意が必要です。
花がらをこまめに取り除いて、風通しをよくすると、発生が抑えられます。
★害虫:アブラムシ、ヨトウムシ、ナメクジ
アブラムシが生育期間を通じて発生します。
よく観察して、株についたアブラムシを冬のうちに手で取り除いたり、薬剤で防除したりしておくと、春以降の発生が少なくなります。
ヨトウムシは春から秋にかけて発生します。
大きくなると、日中は用土の中や株元に隠れる性質があります。
少しでも葉が食害されていたら、夜に見回って捕殺するか、薬剤で防除します。
ナメクジは夜行性です。
見つけしだい、捕殺します。
【用土(鉢植え)】
水はけと水もちのよい、有機物の多い用土を好みます。
赤玉土中粒5、腐葉土3、酸度調整済みピートモス2の配合土などに、リン酸分の多い緩効性化成肥料(N-P-K=6-40-6など)を適量混ぜるとよいでしょう。
【植えつけ、 植え替え】
毎年秋に新しく植えつけます。
【ふやし方】
★種まき:適期は6月から7月もしくは9月です。赤玉土小粒とバーミキュライトの等量配合土など、水もちのよい用土に、タネが重ならないようにまきます。
発芽には光が必要なので、覆土はしません。
幼苗期はナメクジに注意が必要です。秋の彼岸ごろに、3号程度の鉢に鉢上げします。
肥料は薄めの液体肥料(N-P-K=6-10-5など)を施します。
【主な作業】
★花がら摘み:灰色かび病の原因になるので、1月から4月まで花がらをこまめに取り除きます。
花が8割程度咲き終わったら花茎ごと切り取り、下から伸びてくる花茎を育てましょう。
★種取り:4月から5月に行います。
———————————
庭木の剪定や草花の手入れは道具や基礎知識があれば、ご自身でも作業が可能です。
自身で行うのが不安・体力が無く作業が出来ない・忙しく作業の暇がない等、お困りでしたら是非弊社へお任せください!
約10年の腕で迅速・丁寧に仕上げます!
是非お問い合わせください!
———————————